こんにちは。
副編集長のシイノキ(@info_misatopic)です。
三郷市が市内の小中学生1人1台のタブレットを整備する方針なんですって
以前、こんな記事を書きました。
周りのパパママの関心も高く、反響もあったんですが…
「あれって、どうなったの?」
という声がチラホラ聞こえてきていたこともあり、関係者の方にヒアリングしてみたので、ちょいとまとめてみます。
市が小中学生1人1台のタブレットを整備する方針って話どうなった?
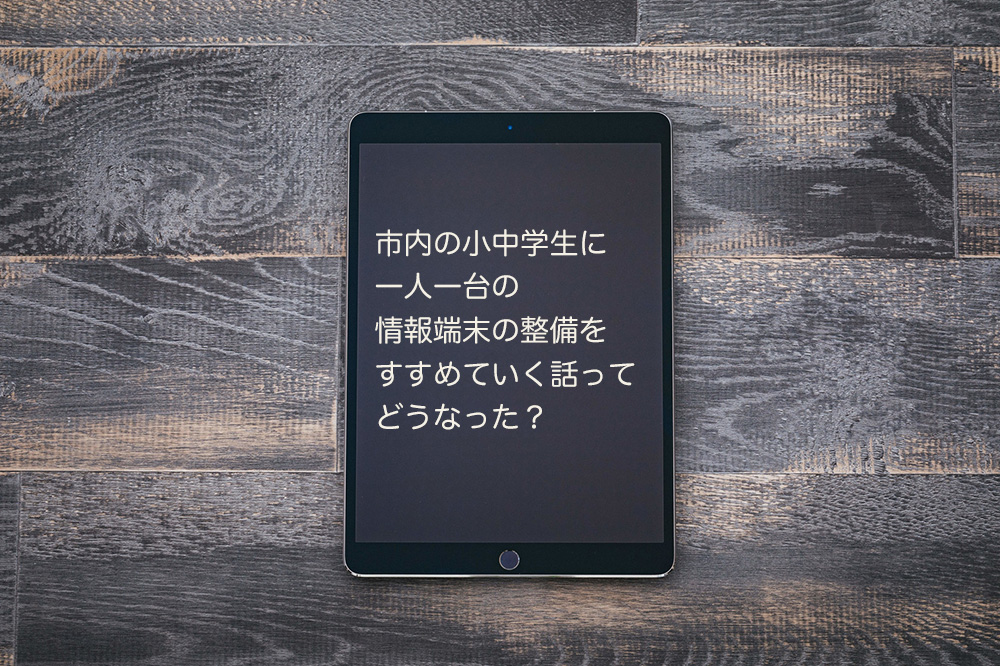
2019年に文部科学省が「GIGAスクール実現推進本部」というものを設置しました。
これは元々は2023年までには義務教育段階の子ども1人につき1台の情報端末、高速大容量の通信ネットワークを整備していこう!って計画だったんです。
GIGAスクールってのはなんぞ?というと…
義務教育を受ける児童生徒のために、1人1台の学習者用PCと高速ネットワーク環境などを整備する五カ年計画でした。
・校内LANの整備
・学習者用PC
・学習と校務のクラウド化
・ICTの活用
具体的にはこんな感じですね。端末支給して校内どこでも使えるようにして、学習内容や校務内容はクラウド化(データはネット上に置いて)して共有しやすくするよ!って感じかと。
で、新型コロナで日本中の学校が休校になったこともあって、
「こりゃGIGAスクールは前倒しでやってくぞ!」
っていう流れの中で、三郷市も「よっしゃ!」となったという経緯がありました。
表記や基準が一定ではないので、支給されるのがパソコンなのか、タブレットなのか、はたまたタブレット型PCなのかは今の所わかりません。
ごめんなさい。
既に配備が始まった地域も出てきて、
「三郷はいつからなの?どうなってるの?ポシャった??」
という声があがってる←イマココ
って感じです。
みさとぴも気になって聞いてまわったところ、上記の三郷市議会の議事録リンクを教えてもらいました。
とは言え、議事録読むのはきっついわ!っていう気持ちが痛いほどわかるので、代表して質疑応答読んでまとめてみます。
そもそもアホなんで、解釈間違ってたら叱ってください。
10月を目標に早急な整備を目指している(6月時点)
スケジュールですが、10月を目標とした早急な整備を目指しているそうです。
とは言え、タブレットやパソコンなどの端末を手配してハイOK!というわけにはいきません。
学校ごとのネット環境の整備(同時接続数も多い)や工事、そのためのスケジュール調整や人員の手配などもあるので、現在のところ早いところでも10末、学校ごとに時期は変わってきそうとのこと。
でもまぁ、具体的な月まで言及されているので、そう遠くないうちに整備されていくんじゃないでしょうか。
今後、秋冬にかけてあり得るかもしれない第2波、第3波の感染爆発への対応のためというのも視野にあるそうですし。
期待。
先生方のオンライン教育支援
臨時校長会や校内研修を行っているところであり、今後も継続して行っていく
ここも大事ですよね。
先生方からすれば、「明日からオリラジあっちゃん的なYouTuberな」って言われるようなもんで。
突然、カメラに向かって授業をしなければならないってのは結構厳しい。
どういう研修やってるのか気になる。
家庭におけるWi-Fi環境等の支援
ネット環境のない家庭は5%〜10%、引き続き研究をすすめる
情報端末はスマホだけ、家にWi-Fiはない!みたいなご家庭もあると思います。
校内のネットワーク環境を利用してもらう等の支援は行ってる学校もあるそうですが、今後は家庭における環境整備支援も関係課と連携を図りながら研究していくということです。
なかなか施策が難しそうですが、まずはネットワーク環境のあるところに来てもらうって形になりそうですね。
個人的な見解なんですが、
・GIGAスクール構想に対応するためには今のネット環境じゃ駄目ですよ詐欺
・ネット環境ないの?任せてもらえれば全部やりますよ詐欺
などが出てくる可能性もあるので、気をつけてくださいね。
ネット環境がない方、現在の環境に不安がある方は、必ず周りに詳しい人がいると思うので、まずは信頼出来る人に相談してください。
障がいのある児童・生徒への支援
ICTを活用することで障がい種に応じた個別指導を充実させることができるよう努める
視力・聴力、発達・身体に障がいのあるお子様はタブレットやPCによる受講が難しいケースがあります。
ICTの活用ってなにさ?ってとこですが…
ICTってのは情報通信技術の使い方のことですね。
ちょっと具体例が難しいですが、文章の読み上げ機能もそうですし、ボタンを押した時の振動で正解不正解を感じ分けるみたいなのもそうですし。
ここらへんは「これがゴール!!」というのがないので、今後も世界共通の課題になっていくと思います。
登校の困難な児童・生徒への活用
必要に応じて貸出しを行い、オンラインによる教員と不登校児童・生徒のよりよい関係づくりに活用していく
今回の対応によって、諸事情で登校出来ていない児童や生徒にも学習の機会が得られるようになるはずです。
これも実施後に新たな課題や問題点なども出てきそうですが、とりあえずは端末は貸し出されると。
タブレットの管理
アクセス制限は家庭との連携を踏まえた研究を進める、故障や劣化による対応もよりよい運営に努める
使うのが子どもですからね。
あくまで学習用の端末なので、好き勝手にアプリ入れられたり、ブラウザでおかしなページアクセスしてウイルス喰らったりしないようにせねばなりません。
やんちゃな子なら戦いごっこの盾に使ったりしそうですし。
いや、この項目の本意は違っていて、端末はツールであり、ツールを使ってなにをしていくのか、どういうツールとして管理していくのかってとこですね。
上記項目を踏まえた教師の役割、指導体制のあり方について
これまでの教育実践の蓄積を大切に継承するとともに、今後はICTを有効活用することで児童・生徒の学びの質を高められるよう、指導、支援をしていく
質疑応答と解釈がチグハグかもしれないですが。
情報端末と情報って、極端に言うと正負プラマイゼロなんですよね。
子どもたちが受け取って解釈をしたところで、質に差がうまれるというか。
先生達には、このツールを使って子どもたちに何を感じて何を学び、活かしていってもらいたいのかっていうのを自分事として考えてもらえたらいいなと思ってます。
個人的な意見ですけど。
これも世界各地の事例とか研究機関の予測とか踏まえつつ研究進めてほしいです。
ICT活用の指導力の向上方策について
今後も指導主事による訪問を継続することで、整備後にも学校差が生じないよう段階的、継続的な研修を支援していく
GIGAスクール構想で教育現場にも大きな変化がうまれるので、大変ですよね。
せっかくなので、オンラインでの学校間の横の繋がりでの情報共有も進められたらいいですよね。
距離や時間も関係なくなりますし、教育機関専門のウィキペディアみたいな集合知メディアみたいなとこでノウハウ共有してみたり。
教育委員会とかも、現場でなにが起こっているのか把握しやすくなりますし。
まとめ
長くなりましたが、保護者としてまず知りたかった、「いつ始まるの?」ってことに対しては
「10月を想定してたけど、早くて10末、段階を追って近々に実施される予定」
ってことらしいです。
小難しいことは学校と行政にまかs……いや、あかん。駄目だ。
これから、僕ら親世代の時代にはなかった教育現場が構築されていきます。
子ども達はとんでもないスピードで順応していきますが、僕らも対応していかないといけません。
・昔ながらの学校が良かった
・なんだかんだ紙の方がいい
・デジタルは苦手だからよくわからない
・よくわからないものだから怖い
って意見も出てくるとは思うんですが、そう遠くない未来に端末すらなくなる時代も来ると思います。
変わっていく現場で子どもたちに何が起きているのか、親として、大人として導く先がどうあるべきなのか、僕らも注視して学ばないといけません。
じゃないと、学校や行政になにを求めていけばいいのかもわからないですからね。
個人的にはアレです。
「教科書忘れちゃったんだけど見せて(ポッ」
みたいな隣の席の子とのロマンスとかもなくなっていく(タブレットに教科書入ってるじゃんみたいなことになる?)のかなと思うと、ちょっとさみしさもあります。
なにはともあれ、記事作成に際してご協力いただいたみなさま、ありがとうございました!
我が家のタブレット
我が家にはタブレットは第4世代iPad miniがありまして。
Apple Pencilで絵とか描いちゃうぞ!っつってペンも買ったんですが……半年前にバッテリー切れたっきり使われてないんです。
なぜなら、誰も絵が得意じゃないから。
最初はね、描いてたんだけどね。
シイノキと1姫くらいだけど。
デジタルなら描けると思ってたら全然だった。当たり前だけど。
今じゃすっかり、電子コミックリーダーになってますね。少年ジャンプとLINEマンガ。
消費するだけじゃなくて、創造をせねば……。
そう、カメラとかスマホとかデジタルガジェットって身の回りに溢れてるけど、使い方によっては金銭的に元が取れるツールでもあるはずなのよ。
安くないからね。
子どもらにも、配給されるタブレットで何をするかってところを意識するようになってもらいたいのよね。
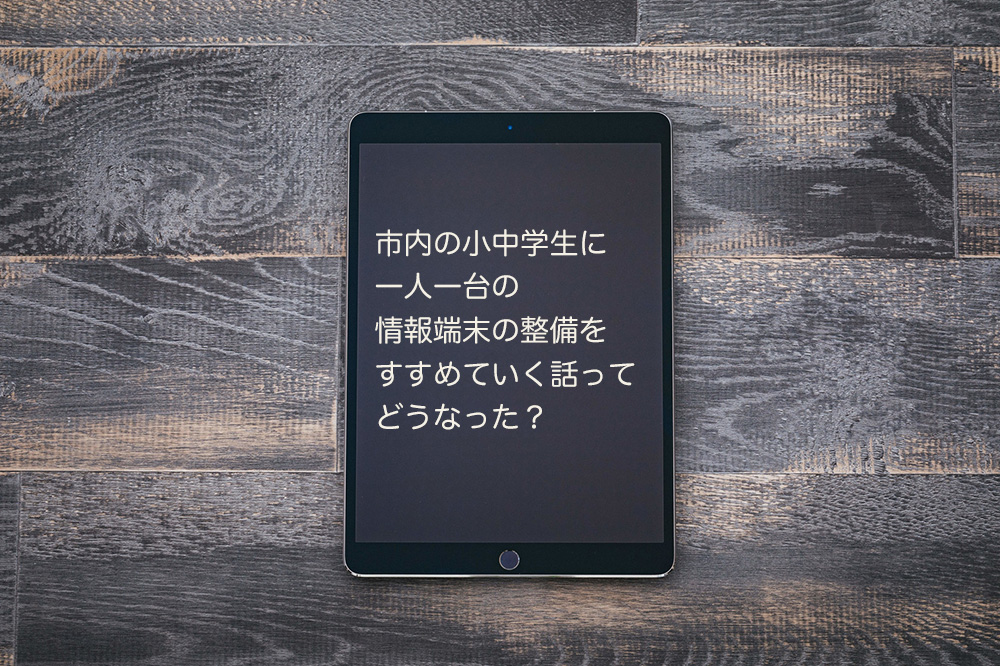
この記事が気に入ったら
いいね! or シェアしてね
みさとぴでは皆さんからの情報提供を募集しています!
みさとぴでは皆さんからの情報提供を募集しています!
リクエストや取材依頼もお受けしているので、どんどんどうぞ!





